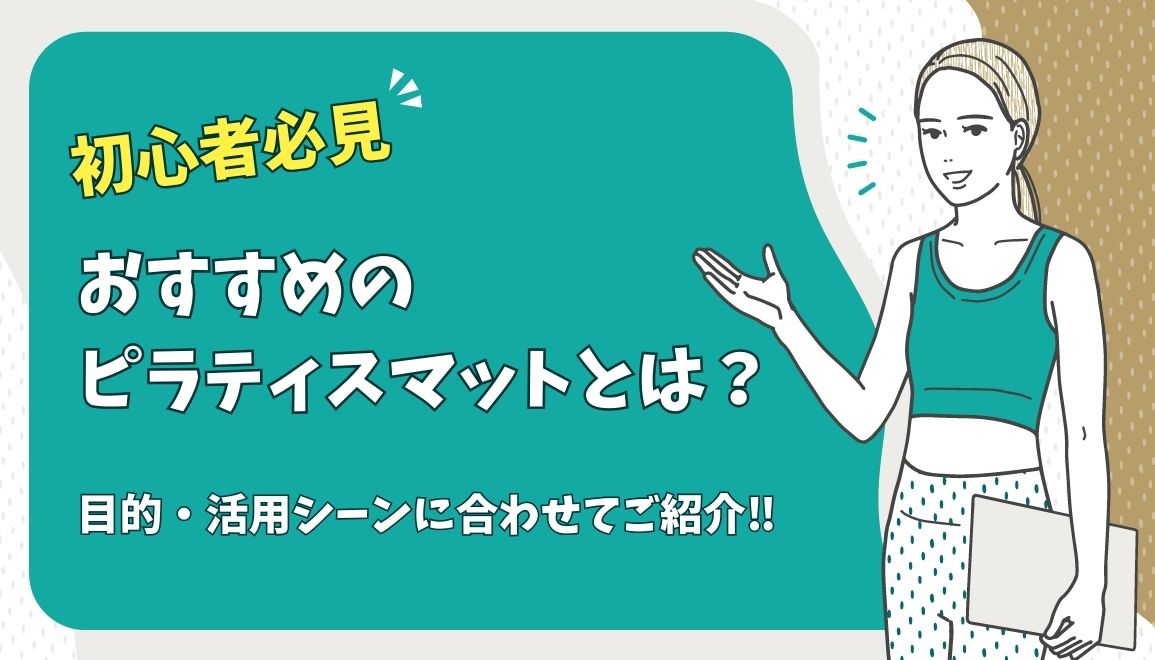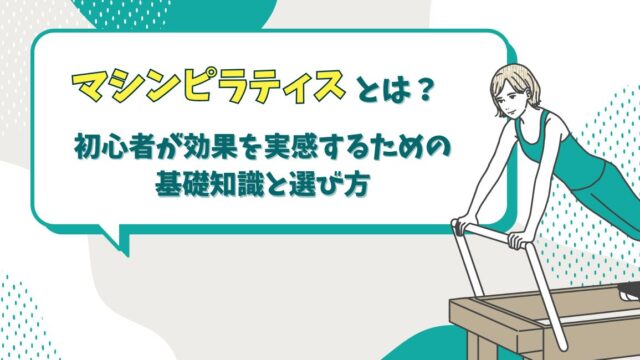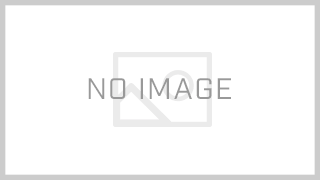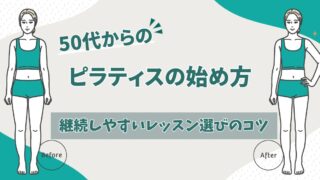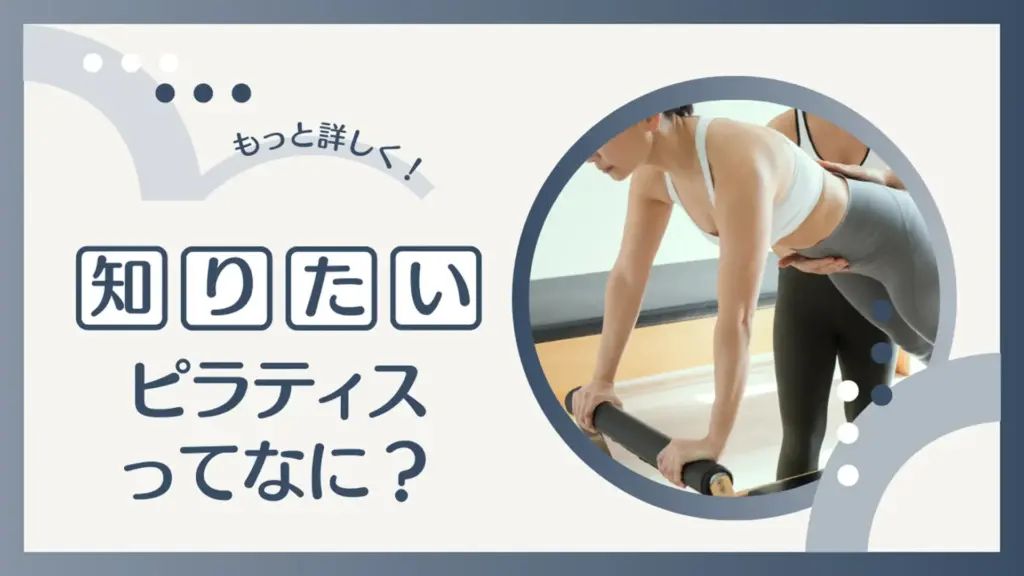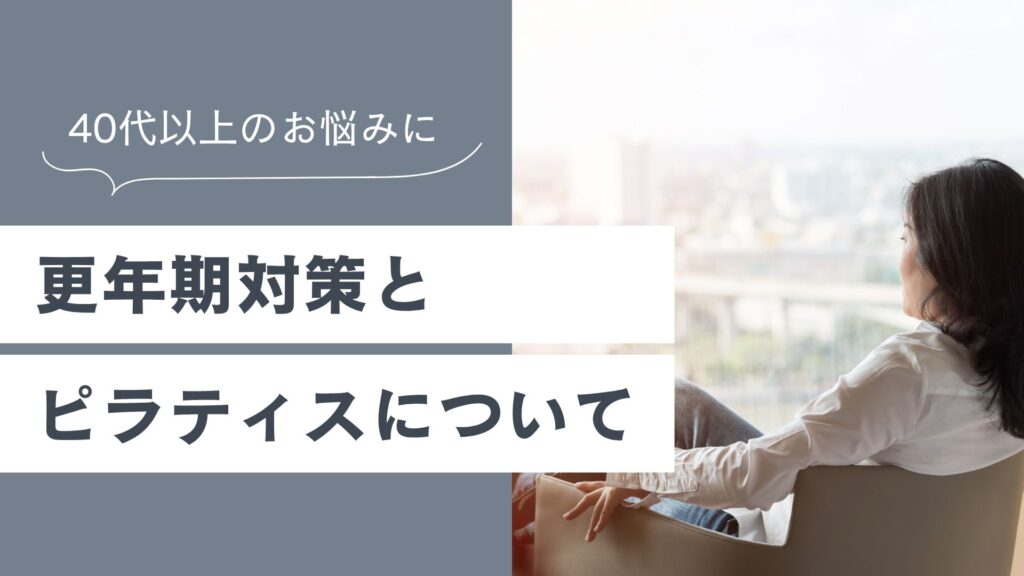ピラティスをこれから始めたい方や、ヨガマットとの違いに迷っている方にとって、最適なピラティスマット選びはとても重要です。
「どの厚みや素材が自分に合っているの?」
「初心者でも失敗しない選び方が知りたい」
そんな疑問や不安はありませんか?
この記事では、人気ブランドや口コミ評価の高いモデルを比較しながら、自分に合った1枚を見つけられるよう、初心者が選ぶべきスペックの目安から、MandukaやLiformeなどの人気ブランドの特徴比較、さらに清掃や保管方法まで、購入前後の悩みに応える内容をお届けします。
あなたのピラティス習慣が快適に始まり、長く続けられる環境づくりに役立つ内容です。
ぜひ最後までご覧ください。
- ピラティスマットの選び方がわかる
- 人気ブランドの特徴を比較できる
- マットの手入れ・寿命と買い替えのタイミング
ピラティス初心者こそ知っておきたい「マット選び」が大切な理由

ピラティスマットは、身体への衝撃をやわらげ、姿勢やフォームを安定させるための「土台」となるアイテムです。
「ヨガマットで代用してもいいのでは?」と思う方も多いかもしれませんが、実際のところ、厚みや滑りにくさなど、使用感には大きな違いがあります。
適切なマットを選ばずに始めてしまうと、「お尻や腰が痛い」「バランスが取りにくい」といった悩みに直結し、せっかくのやる気が失われてしまうこともあります。
ピラティスの動きに適したマットが必要な理由
ピラティスでは、ロールアップやショルダーブリッジ、サイドキックなど、背中・腰・ひざ・骨盤周辺を床につけて動くエクササイズが中心です。
とくに初心者は、筋力や体幹がまだ安定していない状態であるため、マットのサポートがトレーニングの成果を左右します。
厚みが足りないマットを使うと「骨が床に当たって痛い」「動くたびに滑って不安定」と感じ、集中できず継続が難しくなってしまうため、8mm〜15mmの厚みがあり、クッション性が高い素材(TPEやNBR)で、滑りにくさ(グリップ力)にも優れているピラティスマットを選びましょう。
マット選びで効果や続けやすさが変わる理由
ピラティスを効果的に長く続けるためには、「気持ちよく、安心して使えるマット」を選ぶことが重要です。
「使い心地が良い」と感じるマットを選ぶと、トレーニングに対する心理的ハードルも下がり、週に数回でも自然と続けられるようになります。
マット選びは、モチベーション維持にも関わる大切な要素なのです。
単なる道具ではなく、自分の体と向き合う時間を支えてくれるパートナーとして、妥協せず選ぶようにしましょう。
ピラティスマットとヨガマットは何が違う?|知らないと損するポイント

ピラティスマットとヨガマットは見た目は似ていても、実は使う目的や必要とされる性能が大きく異なります。
自分に適したマットを選ぶために、次のポイントを見ていきましょう。
- 厚み・硬さ・素材の違いを比較
- どちらを選ぶべき?目的別の使い分け
厚み・硬さ・素材の違いを比較
まず知っておきたいのが、「厚み・硬さ・素材」の違いです。
これらは使用感に大きく影響し、快適さや効果の出やすさに直結します。
厚みについて
ヨガマットは1㎜~10㎜以上まで幅広くあるのに対し、ピラティス向けとされているマットの一般的な暑さは8mm〜15mm程度です。
マットを使用する場面別でおすすめの厚さは次のとおりです。考
・初心者や自宅での使用を想定している場合
10mm以上の厚みがあるもの。
床の硬さを感じにくく、腰や骨盤、ひざへの負担を軽減できます。
・スタジオに持ち運ぶ用途や、バランス系の動きを重視する場合
8〜10mm程度のやや薄めで安定感のあるものが適しています。
硬さ(クッション性)
柔らかすぎると沈み込みすぎて姿勢が安定せず、逆に硬すぎると床からの衝撃を吸収しきれません。
適度な反発力を持ったものが理想で、素材によって硬さの感じ方は変わるため素材にも注目して選びましょう。
主な素材の特徴は、後述しますが、初心者には軽くて滑りにくい物がおすすめです。
ピラティスマットとヨガマットどちらを選ぶべき?目的別の使い分け
「どんな目的で、どんな場所で使うか」によって、選ぶべきマットは異なります。
ピラティスを中心に行う方、特に自宅で寝転ぶ姿勢や仰向けでのエクササイズが多い場合
厚みがあり、クッション性の高いピラティスマットを選ぶのが基本です。
厚さ10mm前後のマットで滑りにくい素材(TPEや天然ゴム)を選ぶとよいでしょう。
ヨガのように立位やバランスを重視するポーズが多い運動をする方や、軽量で持ち運びやすいマットが必要な方
5〜6mm程度のヨガマットが適しています。
薄手で安定感があるため、体重移動の多い動きでもぐらつきにくく、スタジオ通いにも便利です。
立位のエクササイズ・横になって行うエクササイズの両方を行う方
“やや厚めで滑りにくいタイプ”の中間的(厚さ7〜8mm程度)なマットを選ぶのもよいでしょう。
このように、マット選びは「使い方」と「目的」によって答えが変わります。
自分がどんな運動スタイルを大切にしたいのかを明確にして、厚さや素材をけんとうしてくださいね。
【初心者向け】専門家が解説!ピラティスマットの選び方と比較ポイント

見た目や価格だけで選ぶと、「滑りやすい」「厚すぎてバランスが取りづらい」「持ち運びが不便」などの後悔につながることもあります。
ピラティスマット選びで失敗しないために、初心者が気をつけたいポイントを見ていきましょう。
- まずチェックすべき5つの基本スペック
- 価格帯とコスパのバランスをどう見るか
- 素材別に見る特徴とおすすめ層
まずチェックすべき5つの基本スペック
ピラティスマット購入時の比較ポイントとなる基本のスペックを解説します。
① 厚み(クッション性)
10mm前後の厚みがあると身体が痛くなりにくく安心です。
厚すぎるとバランスが取りづらくなるため、使用目的や体幹の強さに応じて選びましょう。
② 素材
主にTPE、PVC、NBR、天然ゴムなどがあり、それぞれに特徴があります。
たとえばTPEは軽くて滑りにくく、初心者に扱いやすい素材です。天然ゴムはグリップ力と耐久性に優れ、本格的に続けたい人におすすめです。
【素材の特徴】
- TPE(熱可塑性エラストマー):軽量で柔らかく、滑りにくく、初心者に人気。環境にもやさしい。
- PVC(ポリ塩化ビニル):安価で種類が豊富。耐久性はあるが、やや重く滑りやすいものもある。
- NBR(ニトリルゴム):厚みがありクッション性が高い。やわらかい分、やや滑りやすい傾向。
- 天然ゴム:強いグリップ力と耐久性。重さがある。本格派におすすめ。
③ グリップ力(滑りにくさ)
動作中に手足が滑ってしまうとケガやフォーム崩れにつながります。
特に汗をかきやすい方は、グリップ力の高い素材や、表面加工が施されたタイプを選ぶと良いでしょう。
④ サイズ(長さ・幅)
一般的な長さは173〜183cm程度ですが、身長が高い方は長めのマットを選ぶことで、すべての動作を安心して行えます。
幅も60〜66cm程度あると、横向きの動作も安定します。
⑤ 重さ・持ち運びやすさ
自宅専用かスタジオへの持参を想定するかで、適した重さは異なります。
軽量で折りたたみ可能なモデルもあり、使用スタイルに合ったものを選ぶと便利です。
この5つの基本スペックを押さえておくと、見た目や価格だけに惑わされず、自分に本当に合ったマット選びができるようになります。
はじめての方こそ、土台となるスペックをしっかり理解しておきましょう。
価格帯とコスパのバランスをどう見るか
「価格が高い=良いもの」とは限りません。
重要なのは、自分の使い方に対して適正な価格かどうかを考えましょう。
価格帯はおおまかに以下のように分かれます。
- 1,000〜2,000円台:PVC製が多く、価格は魅力的ですが、グリップ力や耐久性に課題がある場合があります。短期間のお試しや、頻度が少ない方には選択肢になります。
- 3,000〜6,000円台:TPE製やNBR製など、軽さ・クッション性・滑りにくさのバランスが取れたモデルが多く、初心者が快適に使いやすい価格帯です。
- 7,000円〜1万円以上:天然ゴム製など、本格志向向けのマット。耐久性・安定感・グリップ力が非常に高く、長く使う予定の方や、インストラクターの愛用品もこの価格帯に多く見られます。
ポイントは、「どのくらいの頻度で、どのような目的で使うか」です。
週に1〜2回の軽めの自宅ピラティスであれば、中価格帯のマットでも十分です。
一方で、「体にフィットする質感」「長期間使いたい」「滑りにくさや耐久性を重視したい」といったニーズがあるなら、多少高くても品質の高いものを選ぶ価値があります。
また、安価なマットを買い替えるよりも、最初から耐久性のあるものを選んだ方が、結果的にコスパが高くなることも多いです。
価格だけに惑わされず、自分の使い方に合った「ちょうど良いバランス」を見つけることが、満足のいく買い物につながります。
迷ったときは、「安心して使い続けられるかどうか」を基準に選ぶと良いでしょう。
素材別に見る特徴とおすすめ
ピラティスマットの使用感や耐久性は、「素材」によって大きく変わります。
見た目が似ていても、素材の違いを理解していないと、「滑る」「すぐへたる」「重くて持ち運べない」といった不満につながりやすく、長続きしない原因に。
代表的な素材と、その特徴・おすすめの人をまとめましたので、素材ごとの特性を把握しておきましょう。
① TPE(熱可塑性エラストマー)
・特徴:軽量でクッション性が高く、滑りにくい。水分を吸いにくいため清掃も簡単。
・おすすめ層:初心者、自宅で使いたい方、軽さや扱いやすさを重視する方。
② PVC(ポリ塩化ビニル)
・特徴:安価で種類が豊富。耐久性はあるが、やや滑りやすく、においが気になる場合も。重さもややある。
・おすすめ層:できるだけコストを抑えたい方。使用頻度が少なめな方。
③ NBR(ニトリルゴム)
・特徴:厚みがあり、クッション性が高い。やわらかく弾力があるが、滑りやすさが出やすい。
・おすすめ層:関節や骨への負担が気になる方。とにかくやわらかさ重視の方。
④ 天然ゴム
・特徴:非常に強いグリップ力と高い耐久性。通気性があり、使い込むほどに馴染む。本格派向け。
・おすすめ層:長期間使いたい方、本格的にトレーニングしたい方、汗をかきやすい方。
用途や体への負担や持ち運びの頻度などを総合的に考え、自分のライフスタイルに最も合った素材を選びましょう。
使用シーン別|あなたに最適なピラティスマットの見つけ方

ピラティスマットは、使う場面に応じて、自分に合うマットは異なります。
というのも、静音性や厚み、持ち運びのしやすさなど、重視すべきポイントはシーンによって異なるからです。
ここでは、より快適にピラティスを楽しめる環境を整えるために、次の使用シーンに分けて解説していきます。
- 自宅で静かに使いたい人に|静音性・厚み重視タイプ
- 持ち運びやすさを優先したい人に|軽量・コンパクトタイプ
- 腰痛・関節の悩みがある人に|高クッション性マット
自宅で静かに使いたい人に|静音性・厚み重視タイプ
集合住宅やマンションで生活していて、動作の際に発生する“床への音”や“振動”をできるだけ抑えたいという方も多いでしょう。
このような場合には、厚み10mm以上のクッション性に優れたマットを選ぶのが効果的です。
厚みがあることで、体重移動やポーズの切り替えによって発生する床への衝撃音を吸収し、下の階への音の響きを抑えてくれます。
特にNBR(ニトリルゴム)素材や、高密度TPE素材のマットは静音性が高く、動きの際の“ドスン”という音を感じにくくなります。
また、フローリングの床で滑りやすさが気になる方は、グリップ力の高い素材(TPEや天然ゴム)を選ぶことで、安定感と静音性の両立が可能です。
マットの裏面にすべり止め加工が施されているモデルもおすすめです。
さらに、防音性を高めたい場合は、マットの下にヨガラグや薄手のカーペットを敷くことで、より効果的に振動を緩和できます。
「家族が寝ている時間に使いたい」「下階への配慮をしたい」と感じている方は、厚みと素材の特性を重視して選ぶことが満足度の高いマット選びにつながるでしょう。
持ち運びやすさを優先したい人に|軽量・コンパクトタイプ
スタジオに通う方や、外出先でもピラティスを続けたい方にとって、大きくて重いマットを毎回持ち歩くのは、想像以上にストレスになり、モチベーションにも影響します。
そのため、移動が多い方には軽量かつコンパクトに丸められるタイプのマットがおすすめです。
具体的には、厚みが6mm〜8mm程度で、重さが1kg以下のモデルが持ち運びやすく、バックに入れてもかさばりにくいです。
素材としては、TPEやPVCが良いでしょう。
比較的軽量で扱いやすく、折りたたみやすいのが特徴です。
また、マットバンドや専用ケース付きのモデルを選ぶと、移動中も快適に持ち運べます。
ただし、軽量なマットは薄くなる分、クッション性や静音性がやや劣る場合があるため、「携帯性」と「使い心地」のバランスを意識して選ぶことが大切です。
通いやすさは継続のしやすさにも直結します。
「できるだけ軽く、スマートに持ち運びたい」という方は、サイズ・厚み・収納のしやすさをチェックして、ライフスタイルに合った一枚を選びましょう。
腰痛・関節の悩みがある人に|高クッション性マット
仰向けで行う腹筋運動や、横向きで体を支える動きは、骨盤やひざ、尾てい骨などが床に直接圧迫されるため、痛みを感じやすくなります。
そのため、厚さ10〜15mm程度で、柔らかく反発力のある高クッション性マットが理想的です。
素材としては、弾力がありながらも身体をしっかりと支えてくれるNBR(ニトリルゴム)や高密度のTPEがよいでしょう。
さらに、マットの幅や長さも広めのものを選ぶと、体の動きに余裕ができ、安定感が高まります。
滑り止め加工がされているモデルを選べば、さらに安全性も向上します。
合わないマットでエクササイズを継続すると、症状の悪化やフォームの乱れにつながる可能性があり、非常に危険です。
腰痛や関節の違和感を抱えている方は、クッション性の高さを最優先に考えることがおすすめです。
人気ブランド6選をプロが比較!各ブランドの特徴とおすすめ層のまとめ

ピラティスマットの6つの人気ブランドを、専門家の視点で比較しながらご紹介します。
ブランドごとの特性を理解し、満足度の高い買い物になるために、次のポイントを整理しました。自分に合う一枚を見つけるための参考にしてくださいね。
- 長く使えると評判のブランド一覧
- ブランド別:初心者〜上級者へのおすすめ度
長く使えると評判のブランド一覧
実際の使用者からの評価が高く、長く使えると評判のブランドを5つ紹介します。
どれも素材の質や滑りにくさ、劣化のしにくさなどに定評があり、初心者〜上級者まで幅広いレベルの方に支持されています。
① Manduka(マンドゥカ)
・特徴:圧倒的な耐久性とグリップ力。天然ゴム素材を使用したモデルが多く、長時間の使用でも劣化しにくい。
・おすすめ層:本格的にピラティスを続けたい中級者〜上級者。
② Liforme(リフォーム)
・特徴:表面の滑りにくさに優れ、汗をかいても安定した動きが可能。素材はエコ素材を使用。
・おすすめ層:自宅でもスタジオでも使いたい方、デザインや環境配慮を重視する方。
③ Yogaworks(ヨガワークス)
・特徴:価格と品質のバランスが良く、厚みのバリエーションも豊富。初心者でも扱いやすい。
・おすすめ層:コスパと扱いやすさを重視する初心者〜中級者。
④ Gaiam(ガイアム)
・特徴:デザイン性が高く、軽量で持ち運びやすい。価格も手ごろ。
・おすすめ層:ピラティス初心者や、週1〜2回の軽めの使用を考えている方。
⑤ prAna(プラナ)
・特徴:ナチュラル素材を使用し、環境配慮型ながらもグリップ力と快適性が高い。
・おすすめ層:素材やエシカル(倫理的)な観点を重視する方。
ブランド別:初心者〜上級者へのおすすめ度
「初心者なのに上級者向けの重く硬いマットを選んでしまった」「やわらかすぎてフォームが安定しない」などといった失敗を防ぐために、ブランドごとのおすすめ度も把握しておきましょう。
主要ブランドの特徴とそれぞれのおすすめユーザー層は次のとおりです。
【初心者向け】
Gaiam(ガイアム)
・おすすめ理由:軽量で扱いやすく、価格も手頃。カラーバリエーションやデザインも豊富で、はじめての1枚に最適。
・適している人:週1〜2回の自宅用、まずは試してみたい方。
Yogaworks(ヨガワークス)
・おすすめ理由:厚みや素材の選択肢が豊富で、クッション性と安定感のバランスが良い。使いやすさ重視の設計。
・適している人:継続したい初心者、自宅とスタジオ両方で使いたい方。
【中級者向け】
TIGORA(ティゴラ)※スポーツ量販店ブランド
・おすすめ理由:機能性に優れつつ価格も抑えられており、定期的な使用にも耐えられる。
・適している人:週2〜3回使う習慣ができてきた方。買い替えを検討している方。
prAna(プラナ)
・おすすめ理由:環境に配慮した素材と、安定したグリップ力・快適性を両立。デザインも落ち着いており、継続意欲を高めてくれる。
・適している人:本格的に習慣化し始めた人、素材にもこだわりたい方。
【上級者向け】
Manduka(マンドゥカ)
・おすすめ理由:高密度素材と圧倒的な耐久性で、10年以上使えるとのレビューも多い。フォームの安定感に定評あり。
・適している人:週3回以上、強度の高いピラティスを行う人、プロ志向の方。
Liforme(リフォーム)
・おすすめ理由:滑りにくさとデザイン性の高さを両立。高価だが満足度が高い。
・適している人:スタジオや指導での使用を前提とする方、グリップ力を最重視したい方。
このように、ブランドごとに適したユーザー層や機能性が明確に分かれています。
「見た目の好み」だけで選ばず、自分の習熟度や使用目的に合わせて選ぶことで、より満足のいくマット選びができるでしょう。
段階に応じてブランドを見直すのも、継続のモチベーション維持につながります。
長く使うために|ピラティスマットの手入れ・寿命と買い替えのタイミング
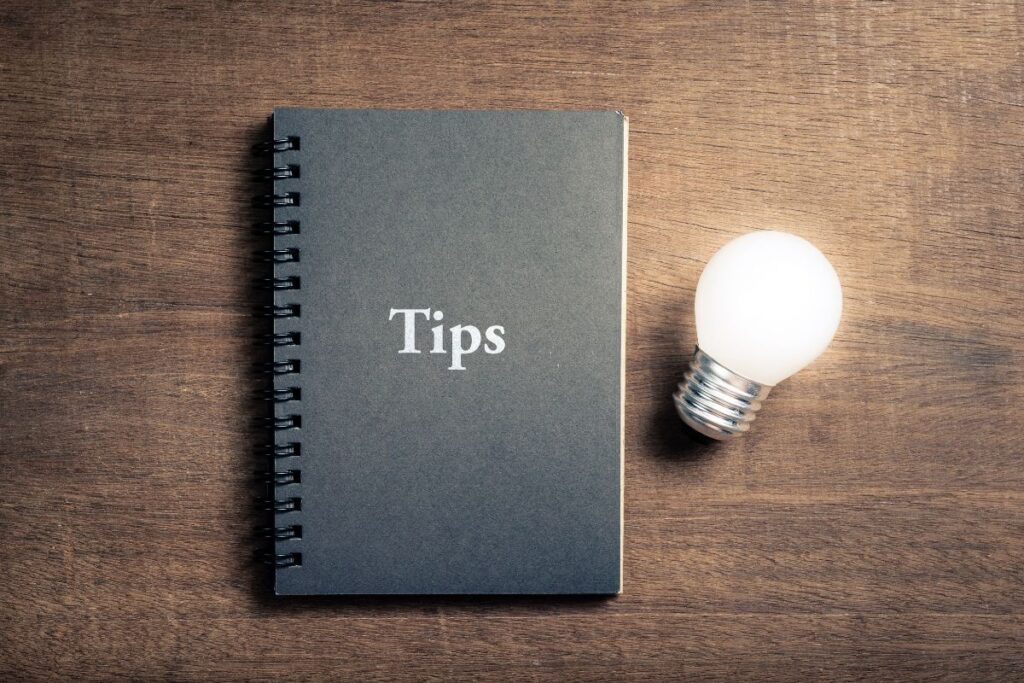
ピラティスマットを長く快適に使うための手入れ方法と、寿命や買い替えのタイミングについて解説します。
実際、適切なケアを怠ると、表面の劣化や臭い、滑りやすさの悪化が起きやすく、思わぬトラブルや怪我の原因になることもあります。
そのため、ここでは以下の内容を順にご紹介します。
- 清掃しやすいマット素材とは?
- 買い替えの目安とマットの寿命
- 長く使うための正しい保管・お手入れ方法
清掃しやすいマット素材とは?
ピラティスマットは床に直接触れるうえに、汗や皮脂も付きやすいため、放っておくと臭いや劣化の原因になります。
清掃がしやすく、初心者にも扱いやすい素材は、TPE(熱可塑性エラストマー)やPVC(ポリ塩化ビニル)です。
・TPE
水分を吸い込みにくく、アルコールや中性洗剤を使って軽く拭き取るだけで清潔を保てます。乾きも早いため、毎日のケアが負担になりません。
・PVC
TPEと同様に水分が染み込みにくく、表面がつるっとしているため、汚れが落ちやすい特性があります。価格も手頃で、初心者が最初の1枚として選びやすい素材です。
一方で、天然ゴム素材やNBR素材は、吸水性が高いためお手入れしにくい傾向にあります。
・天然ゴム素材
吸水性が高く、拭き掃除後の乾燥に時間がかかる上、アルコールや強い洗剤が使えないため、丁寧なケアが必要です。
・NBR素材
クッション性に優れる反面、水分が染み込みやすい構造のため、汗をかきやすい方や毎日使う方にはやや不向きな面もあります。
衛生的に使い続けるためには、「素材の清掃しやすさ」+「日常的なケアのしやすさ」の両面からマットを選ぶことが重要です。
特に毎日のように使う方や、忙しくて掃除に手間をかけたくない方には、TPEやPVC素材のマットが最適でしょう。
ピラティスマットの買い替えの目安と寿命
ピラティスマットは一度購入すればずっと使えるものではありません。
使用頻度や素材によって劣化のスピードは異なり、適切なタイミングで買い替えることが、快適で安全なトレーニングを続けるために重要です。
一般的なマットの寿命は、週に2〜3回使用する場合で6ヶ月〜1年程度です。
ただし、素材や使い方によって差があり、耐久性の高い天然ゴムや高密度TPE素材のマットであれば、1年以上使えることもあります。
一方、PVCやNBRなどは価格が手頃な分、表面の劣化やへたりが早く、半年以内に傷みが目立つこともあります。
買い替えの判断ポイントとしては、次のような状態が見られたときが目安です。
- 表面がひび割れてきた、削れて粉が出る
- グリップ力が低下して手足が滑りやすくなった
- 厚みが均一でなくなり、部分的に薄く感じる
- 汗や湿気によるにおいが残り、拭いても取れない
- 体を支える感覚がなくなり、痛みを感じやすくなった
これらのサインが現れた場合、マットの性能が落ちており、ケガやトレーニング効果の低下につながる可能性がありますので、このような状態になっていないか定期的にチェックしましょう。
ピラティスマットの正しい保管・お手入れ方法
ピラティスマットを長く快適に使い続けるための、正しいお手入れと保管方法を解説します。
【日常のお手入れ方法】
使用後に中性洗剤を薄めた水またはアルコールフリーの除菌シートなどで表面をやさしく拭き取ることが基本です。
汗や皮脂はカビや臭いの原因になるため、使ったらその日のうちに一拭きする習慣をつけましょう。
素材ごとの注意点としては、天然ゴム製のマットは水分に弱く、強い洗剤やアルコールの使用がNGです。必ず専用クリーナーか、湿らせた布でやさしく汚れを拭き取りましょう。
【保管のポイント】
水で濡らした場合は、完全に乾いてから収納し、収納場所の環境としては直射日光の当たらない風通しの良い場所がおすすめです。
また、重いものを上に載せたり、折りたたんだまま放置すると型崩れの原因となるため注意しましょう。
巻いて保管する場合は、内側に使用面を向けて巻くと表面のカールが出にくくなります。
マットは毎日身体を支える大切な道具です。
ちょっとしたケアと保管方法の工夫によって、寿命が1年以上変わることもあります。
お気に入りのマットを長く使うために、日常的なメンテナンスを大切にしましょう。
FAQ

Q1:ピラティスマットは「10mm」と「15mm」、どっちを選べばいい?
A:
どちらが良いかは「使用場所」「体への負担」「体幹の安定感」のバランスで決まります。
10mmはほどよいクッション性と安定感の両立ができ、体幹トレーニングを重視したい方やスタジオでの持ち運びがある方におすすめです。
一方、15mmは床からの衝撃をより和らげるため、腰痛や関節に不安がある方や、静音性・快適性を重視して自宅で使う方に向いています。
厚みが増すと柔らかくなりすぎてバランスを取りづらくなるため、使用目的を明確にして選びましょう。
Q2:ニトリのヨガマットってどう?初心者にもおすすめ?
A:
ニトリのヨガマットは、価格が手頃で入手しやすい点が魅力です。
素材は主にPVCやTPEで、扱いやすいため、初心者が自宅でゆるやかに始めるには適しています。
ただし、グリップ力や耐久性は中価格帯〜高価格帯の専用ブランドと比較するとやや劣るため、頻繁に使う予定がある方やフォームをしっかり意識したい方は、TPE素材や天然ゴム製の専用マットも検討するとよいでしょう。
Q3:「Balanced Body」のマットってプロ向け?初心者でも使える?
A:
Balanced Body(バランスドボディ)は、ピラティス専用器具や教育プログラムを提供している米国の老舗ブランドで、インストラクターや養成コース受講者にも選ばれている高品質マットを展開しています。
滑りにくさ・耐久性・体のフィット感など、品質は非常に高く、プロからの信頼も厚いです。
初心者でも使えますが、価格が高めでやや重さがあるため、「本格的に続けたい」「長期的に使えるものを選びたい」という意志がある方に特におすすめです。
最初の1枚として使う場合は、他のマットと比較して納得の上で購入しましょう。
Q4:滑らないピラティスマットを選ぶには何を重視すればいい?
A:
滑りやすさは、動きに集中できなくなるだけでなく、フォームが崩れてケガの原因にもなります。
マットを選ぶ際は、「素材」と「表面加工」に注目しましょう。
特におすすめなのは、TPEや天然ゴム素材。
これらは床としっかり密着し、汗をかいてもグリップ力が落ちにくいのが特徴です。
また、表面にエンボス加工(凹凸模様)や波型テクスチャがあるマットは、手足のズレを防ぎやすくなります。
実際、インストラクターや上級者の多くが「滑りにくさで選ぶなら天然ゴム」と回答しています。
「脚が広がるポーズでズルッと滑るのが怖い」「汗っかきで安定しない」などの悩みがある方は、素材と加工の両面からチェックして選びましょう。
Q5:おしゃれなピラティスマットって実用性も兼ね備えているの?
A:
はい、近年は「機能性」と「デザイン性」の両立が進んでおり、選択肢が広がっています。
LiformeやGaiamなどのブランドでは、北欧風や自然モチーフなどの美しいプリント入りマットが人気で、トレーニングのモチベーション向上につながるという声も多いです。
ただし、“見た目だけで選ぶ”と失敗するケースもあります。
たとえば、デザイン優先でPVC製の薄手マットを選ぶと、滑りやすく関節が痛くなることがあります。
選ぶ際は「TPE素材で厚み10mm以上」など、最低限の機能性を満たしていることを確認しましょう。
おしゃれなマットはSNS映えもするため、継続のきっかけになりやすい点も魅力です。
部屋のインテリアに調和するデザインを選ぶと、毎日の習慣に自然に溶け込ませやすくなります。
Q6:折りたたみ式のマットはロールタイプよりおすすめ?
A:
一長一短ですが、「収納スペースの確保」と「使い心地」のどちらを優先するかで選び方が変わります。
折りたたみ式は、畳んで家具のすき間に収納できるため、ワンルームなど狭い空間で使う方には便利です。
軽くて持ち運びやすく、最近では6〜8mm厚で滑り止め付きの実用モデルも増えています。
ただし、折り目の段差やズレが気になるという声もあり、寝転がる動きや体幹トレーニングでは違和感を覚える人もいます。
そのため、自宅据え置きで本格的に取り組みたい場合は、ロールタイプ(巻くタイプ)のほうが快適性が高く、体の安定感も得やすいです。
「たまに使いたい」「すぐ片付けたい」「旅行にも持って行きたい」といった方は折りたたみ式が◎、
「週3以上使う」「フォームを正確に意識したい」方はロールタイプがおすすめです。
自分にあうマットで快適なピラティスライフを送ろう

自分にあったピラティスマットは、無理なくピラティスを続けるための必須アイテムと言っても過言ではありません。
マットの違いがわかるようになると、自宅での快適さも、トレーニングの質も大きく変わってきます。
- 初心者は、まず厚み10mm前後・滑りにくい素材のマットから始めると安心
- 使用シーンに応じて、静音性・持ち運びやすさ・クッション性などを重視して選ぶ
- TPEや天然ゴムなど、素材の違いは耐久性や手入れのしやすさに直結する
- 人気ブランドの特徴を知ることで、価格と機能のバランスが判断しやすくなる
- 使用後の清掃・保管方法を知っておくと、寿命を伸ばして衛生的に使える
- 自分の目的(姿勢改善・運動習慣・腰痛対策など)を明確にして選ぶのが成功の鍵
マットは、エクササイズ中の体を支える土台です。
「見た目」や「価格」だけでなく、使い心地・安全性・継続のしやすさを考えて選ぶことが、ピラティスがもっと楽しく、生活の一部になっていくでしょう。
あなたにぴったりの1枚が見つかることを願っています。

この記事の著者・運営者:マシンピラティススタジオ ルルト